|
|
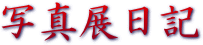
98年6月
6/07/98 (日)
写真展の案内状をそろそろ送る時期になってきた。ポストカードをそのまま送る方法もあるが、この方法だと挨拶やオープニングパーティ等の情報を書き切れないので、私はいつも別途用意した挨拶状と一緒にポストカードを封筒に入れて送るようにしている。 そこで、まずこの挨拶状印刷用の紙と封筒を探した。
たまたまこの日は横浜に行く機会があったので東急ハンズで探してみた。まず、ポストカードが丁度入る大きさの封筒を200枚購入した。また、挨拶状にちょうとよいA5サイズの紙があったので購入した。半分に折ると購入したポストカードに丁度入る大きさだ。結婚式の2次会等の案内でも使えそうな紙で一枚25円、合計200枚。 この後、案内状を作成し宛名書きが必要だ。作業量は年賀状を出すのと同じ程度だろう。
6/10/98 (水)
会場でインターネット接続を行うために、株式会社ピープルワールド(PWC)の丸山さんにお会いした。丸山さんには、私がPeopleのPhoto Plazaという写真のフォーラムでプロデューサーを担当していた頃からお世話になっており、今回の企画も既に何度かメールでご相談していた。写真展の主旨とインターネット連携の狙い、会場でインターネットに興味を持たれた写真愛好者の方々に対してPeopleの紹介を行ってもよい旨ギャラリー側の合意をいただいていること、等をご説明し、会場へのインターネット回線と関連機器の提供をお願いしたところ、ご快諾頂いた。
具体的には、以下の通り行う事にした。
- パソコンは私が個人で所有しているThinkPad 535を使用し、ディスプレイ・通信関係機器・他はPWCが提供
- ハードディスク上に最新の私のホームページのファイルをコピーしておく。通常はこちらを表示
- 私の他ホームページへのリンクから他の写真関連ホームページに飛べるように、PHS経由でインターネットに接続する。32K bpsで接続できるので、それなりに快適にネットサーフ可能
- 私のThinkPad 535上の不要なアイコンは予め消しておく。これは、不要な操作を行われないようにするため
これで、今回の写真展の目玉の一つである写真愛好者の方々にインターネットでの写真の楽しみ方を伝える企画が実現できる事になる。丸山さんに感謝。
6/11/98 (木)
Yahoo Unplugged!というサイトのMark Smalleyさんのコラムで、私のホームページが紹介された。4つ星をいただいた。紹介文を読むと、ちょっと恥かしいような....。お時間がある方はご覧ください。
6/12/98 (金)
今まで雑誌等に掲載された記事をまとめてファイリングしてみた。
初めて雑誌で私の写真展が紹介されたのは'89年7月、今はもう廃刊になっている「The Where」という首都圏のイベント雑誌だ。その次はちょっと時間を置いて'92年6月の「Canon Circle」というキャノンが同社の会員に発行している雑誌にカラー2ページ見開きで紹介。'93年は様々なパブリシティで取り上げていただいた。学研のカメラ月刊誌「CAPA」、マガジンハウスの「BRUTUS」、「ポパイ」で写真展の簡単な案内を、日経ホーム出版の今はなき「日経アントロポス」でカラー見開き2ページで特集記事を、日本写真企画の写真月刊誌「フォトコンテスト」で3ページのインタビュー記事を掲載いただいた。
改めて色々な雑誌で取り上げていただいていることを感じさせられる。 このファイルは、参考資料として写真展会場に置く予定だ。
6/13/98 (土)
案内状を送るために住所を再度チェックした。今年の初めに全国で郵便番号が変わったので、今年の正月いただいた年賀状で郵便番号を再入力し、住所変更等を反映した。 また、既に写真展の連絡を行っている人を削除した。 これで差込み印刷を行えば封筒への宛名書きはOK。 夜も遅くなり、近所にプリンターの音で迷惑をかけるので、明日印刷することにする。 また、挨拶状も作成した。
色々な準備作業を行っていると、改めて結婚式や披露宴等の準備と似たところがあると実感させられる。
6/15/98 (月)
学研CAPA編集部の長瀬副編集長から電話をいただき、5月17日に打ち合わせた内容を元に、CAPA7月号の記事が出来上がったとのお知らせ。ゲラ刷りをFaxしていただいた。モノクロ見開き2ページだ。「写真展FAQ」に掲載しているボリュームのある内容がどのように2ページに収まるのかと思っていたのたが、余分な言葉はカットし、強調すべきところは強調し、イラストも入って読み易く、2ページにきれいに納まっている。 やはり編集のプロの仕事は素晴らしい!
6月19日に発売されますので、是非ご覧ください。
6/17/98 (水)
準備した案内状を郵便局に持っていって郵送した。「料金別納」のハンコを押し、郵便局の窓口に持っていってまとめて料金を払う。時間がかかる作業なので平日には行えないのだが、今日は会社の創立記念日で休みだったので助かった。 他にも何個所か案内状を送付予定だが、案内の方はほぼ目処がついた。
後は、ポートフォリオケースに入れている作品40点を取り出しマット加工した台紙に貼り付けてフレームに装丁し、PCをセットアップし、インターネット関連の説明パネルを作成する作業と、作品やパネルを会場まで搬送する作業、及び、開催前日の準備(セットアップとオープニングパーティ)が残っている。開催前日はオープニングパーティもあって夜遅くまで長い一日になりそうなので、渋谷にホテルを予約して泊まる予定だ。
6/19/98 (金)
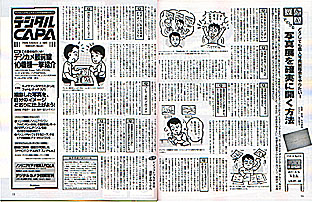
 本日発売の写真月刊誌「CAPA」に記事が掲載された。
本日発売の写真月刊誌「CAPA」に記事が掲載された。

左のように、一つは「Q&Aでわかる写真展を確実に開く方法」という見開き2ページの記事。「監修・写真/永井孝尚」となっている。記事の内容は、私が正月に作成したFAQの内容に基づいており、FAQの中から写真展審査の部分に特に焦点を当てて編集部で編集し直したものだ。ゲラ刷りを見た時も感じたが、よくこれだけの限られたスペースにこれだけの多くの情報をイラストをうまく使いながら見やすく配置できるものだと、プロの編集の仕事に改めて感心させられる。ゲラ刷りとほぼ同じ内容だけれども、雑誌に掲載していただく場合はいつもそうだが、書店で実際に印刷所のインクの匂いがかすかにする雑誌を手に取ってみると改めて感慨が深い。
もう一つは写真展案内のコーナーでの紹介記事だ。サンディエゴで撮影した親子の写真を使っていただいている。
雑誌に掲載していただく時は、やはりアマチュアだからだろうか、いつも1週間前位から楽しみでしょうがない。
6/21/98 (日)
今朝の時点でポートフォリオケースに入っている40点の作品はすべて写真展で実際に展示するものだ。展示するためにはこれらを全てマットにマウントして額装する必要がある。写真展まで残りが丁度1ヶ月だが、今後1ヶ月のスケジュールを考えると、写真展直前の数日を除けば丸一日間程のまとまった時間が取れるのはこの週末しかない。
既に40点の大衣の額と、額とプリントのサイズに合わせてカットした40点のマットはGW中に用意している。作業は以下の手順だ。
- ポートフォリオケースからプリントを抜き出す。ギリギリのサイズに入っている上に密着しているので、プリント作業用の手袋をはめて注意深く作業する。
- 無酸性テープでプリントをマットに裏側からマウントする。
- 大衣の額に入れる。尚、額のガラスは展覧会場の照明の関係で作品が見にくくなるので外しておく。
6/30/98 (火)
前日、私が今の勤務先に新入社員として配属になった時に同じ部門にいらっしゃって数年前に退職された福住さんから電話をいただいた。 福住さんはご自身でも本格的な写真をお撮りになり、自宅にはカラー用暗室まであったり、自作カメラがコンテストに入賞したりする等、非常に写真に造詣が深い方だ。 現在、株式会社カルチという会社を経営されており、個人向けの写真集の製作・販売を行ったり、在職中の経験を活かして文字フォント製作・販売等を行ったり、データ入力や図面・文書の電子化サービスを提供したり、と、幅広く事業を展開されている。 私が過去3回の写真展を行った際にも、いつも会場に作品を見に来て下さっていた。
電話の内容は、現在新規開発中の写真集製作サービスのサンプルとして写真集を作ってみないか、ということだった。現在、福住さんは「カルチブック」という写真集製作サービスを行っており、富士写真のピクトログラフィーを使用した非常に画質が高い写真集を製作されているが、大量部数作成に対応できないという問題もあって、IBM社のフルカラーオンデマンド印刷とご自身で持っている特許技術を組み合わせ、新しくローコスト・大量部数対応の写真集製作サービスを開発されている。 現時点である程度の技術的な目処がつき、何かよいサンプルがないか考えていたところへ、私の写真展の案内状が届き、早速電話を下さった次第だった。
写真集の製作料は通常20−30万円かかるところを無料とし、15部程を私に下さり、その代わりに別途作成した写真集を新しい写真集製作サービスのサンプルとして株式会社カルチで使用する、というものだ。 私自身まだ写真集を製作した経験がなく、非常に魅力的な話で、電話では「是非よろしくお願いします」と答えた。
この日は会社の仕事を6:00PMまでに終え、すぐに近くにある株式会社カルチまで足を運んだ。 今までに作成されたピクトログラフィを使用した写真集や、新しく開発中の写真集の試作版をいくつか見せていただき、サービス概要等も教えていただいた。 お互いに写真好きということもあり、写真談義等にも花が咲く。気が付くと2時間以上話し込んでいた。
結論として、写真集製作を行うことになった。写真展まで3週間しかなく、それまでに間に合わせるためには早速作業を始める必要がある。このために、実際に作業を担当される酒井さんの仕事のスケジュールも翌日から空けて下さっているとのこと。まず、スキャナーで読み込むためのプリントをお渡しした。また、写真集のレイアウト用原稿のレイアウトシートをいただいた。 写真集のことを話す時の福住さんはとても楽しそうで、本当に仕事を楽しんでいらっしゃるのが分かる。 福住さんとお話しする時はいつも「仕事はやっぱり楽しまなければ」と思う。
この写真集製作サービスは他社の同様のサービスと比べて、いかにも写真が本当に好きな人が考えたサービスであると思わせる良心的な点が数多い。例えば、
- 通常ピクトログラフィーのプリントはベースのペーパーの色が変わり易いのだが、特殊技術により変色を防いでいる。
- 1ページ写真を3点まで入れても1点の時と値段が変わらない。他社では1点増えるごとに別料金になる。実際にレタッチの手間を考えると、持ち出しになってしまうそうだ。
- 画質には時に配慮しており、オフセット印刷等と比べてトーンが美しく表現できる。
- 写真原稿の配送には30万円までの保険を掛けている。他社では保険を掛けず、デュープ入稿を勧めるケースが多い。
自宅に戻って早速レイアウトシートを使って原稿を作成する。写真点数は写真展と同じ40点、それに最初のページのタイトルと、2ページ目の前書き、40点の写真を1点1ページに配置し、43ページ目に全作品のデータ、44ページ目に作者略歴、と、合計44ページになる。それぞれのレイアウト及び文を作成する。 このような作業の際には、ホームページ上等にデータがまとめられていることで非常に効率的に作業を進められる。 9:30PMから作業を始め、2時間で作業を完了した。 ゼロからデータを作っていたら1週間かかっていただろう。